
肋骨の中には横隔膜がありその中に肺や心臓があります。
これらは呼吸をするための大事な中枢ですね。
下部肋骨は浮遊していることもあり
放っておいてもよく動きますが
中部から上部は日頃から動かすように
しないと固まりやすいのです。
特に上部は鎖骨と連結しており
ここが固まらないように動かしていくこと
が深い呼吸をする上でとても大事なことです。
今回はこの上部肋骨の動かし方を
順に説明していきたいと思います。
上部肋骨の場所と肋骨の動き方を知ろう
肋骨には上部・中部・下部の3つの
部位に分けられるとは言いましたが
解剖学的に明確な区切りが
あるわけではありません。
肋骨は全部で12個の
骨にわけられますので
今回はおよそ3等分するような
イメージで進めていきます。
上部肋骨(第1~3肋骨)
中部肋骨(第4~7肋骨)
下部肋骨(第8~12肋骨)
場所は画像を参考にして頂ければと思います。
(後面からの肋骨)
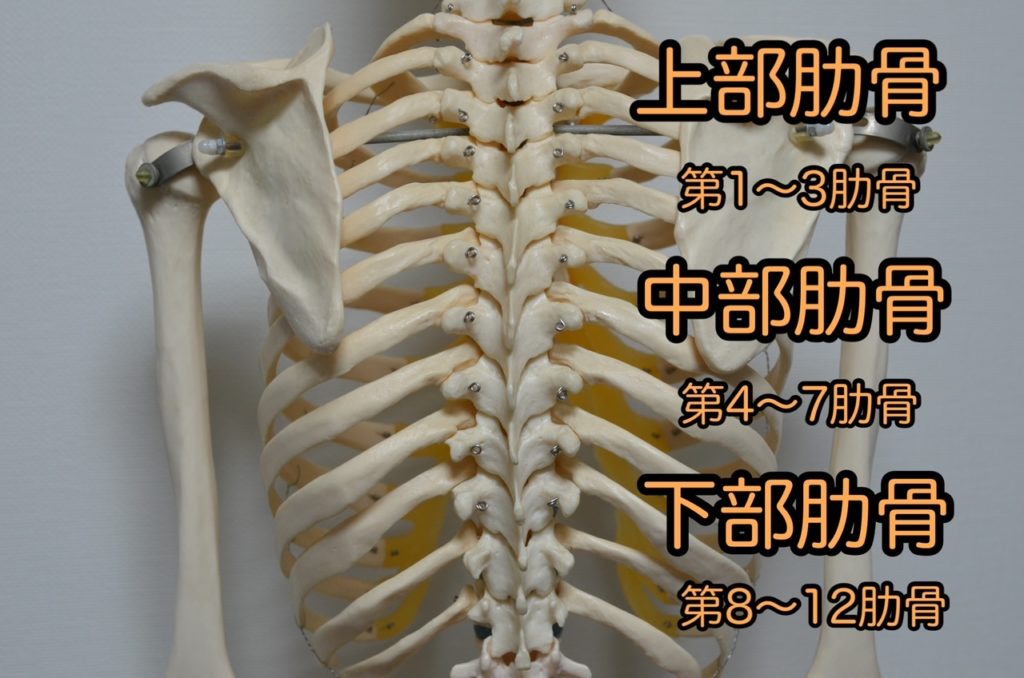
(前面からの肋骨)

また肋骨は伸展・屈曲・前方回旋、後方回旋の
4つの動きに大きくはわけられます。
屈曲は猫背のように背中を前へと倒す動作
伸展は胸を後ろへと反らす動作
前方回旋は鳩尾のあたりを
起点にして上と下に分けます。
回旋なので上(上部肋骨)と中(中部肋骨)と
下(下部肋骨)にわけた肋骨を順番に前と後ろへ回します。
回旋は少しわかりにくいかと思いますので
よければ図を参考にしてください。
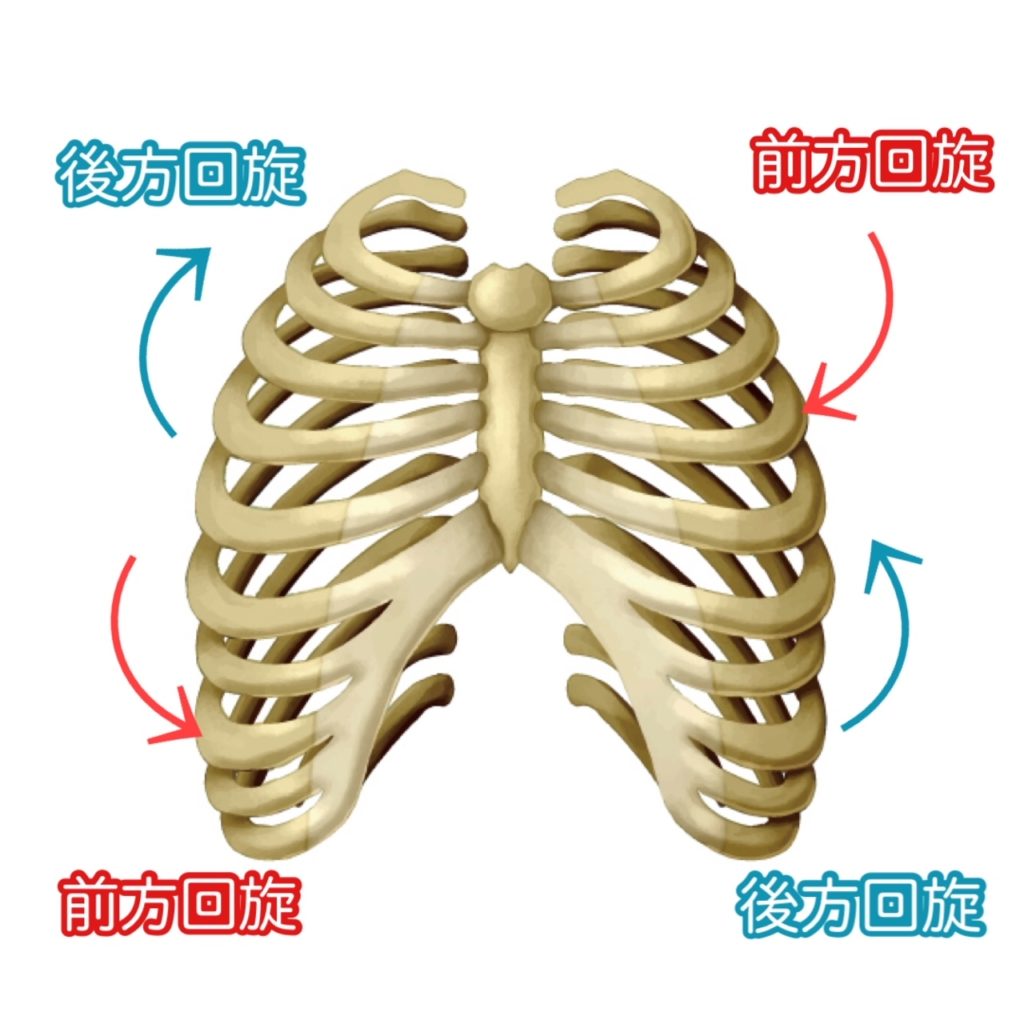
肋骨の動きが良くなるとどんな効果が⁉
肋骨の動きがよくなると様々な効果や
体のパフォーマンスアップに繋がります。
どんな効果があるのか紹介したいと思います。
肋骨の動きが良くなるとこんな効果が
- 肋骨の動きが良くなると肺の膨らむスペースができて呼吸が深くなる
- 背中や肩甲骨まわりの筋肉が緩んで動作が楽になる
- 肋骨まわりの筋肉が緩んで結果的に姿勢がよくなる
- 呼吸が深くなることで全身への血流や酸素供給量が増える
- 体が疲れにくくなり寝起きもよくなって回復力があがる
肋骨まわりが緩んで動きがよくなるだけで
筋肉や内臓、姿勢などにさまざまな良い効果が期待できます。
上部肋骨を動かすための方法
肋骨には上部・中部・下部に
わけられると冒頭で紹介しました。
下部肋骨は動きやすいので
固まることはほとんどありません。
反対に中部から上部の肋骨は動きが制限されやすく
固まっている方が多い印象です。
今回はその中部から上部の肋骨を固めないように
日ごろからできる運動を紹介したいと思います。
※まず胸骨と鎖骨をつなぐ
胸鎖関節の場所をイメージしてください
ここが上部肋骨を動かすための起点となります
(ちなみに腕はこの胸鎖関節からはじまります)
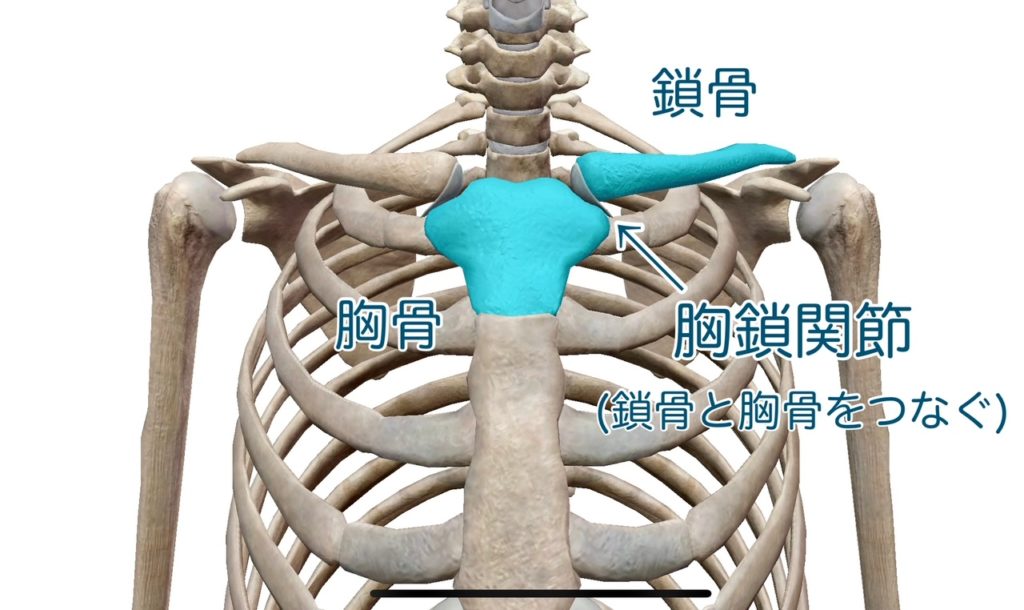
①胸鎖関節を起点にして前後に動かします
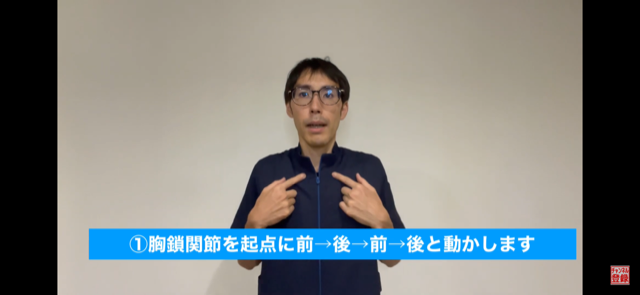
②胸鎖関節を起点にして上下に動かします
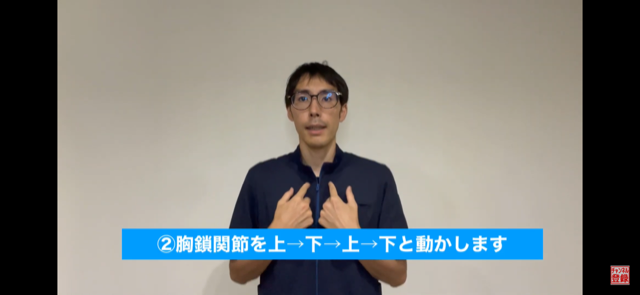
③胸鎖関節から前に回します
(動かすときに余計な力が入らないように注意します)
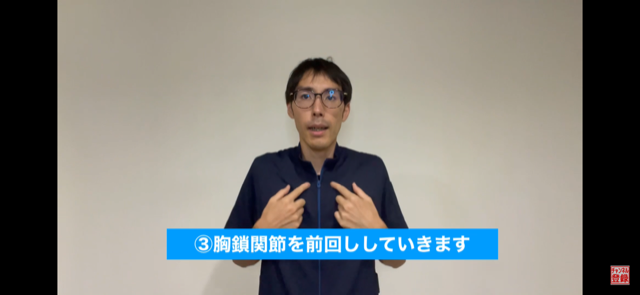
④胸鎖関節から後ろ回しもします
(結果として肩関節も一緒に回ってきます)
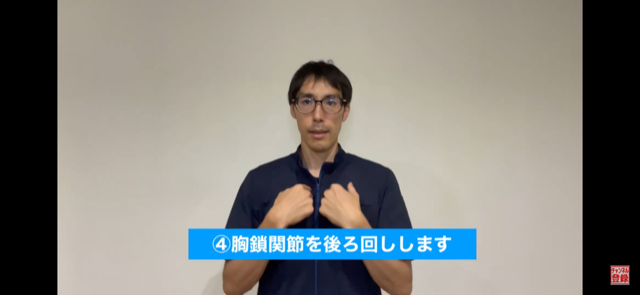
次に中部肋骨を動かしていきます。
基本的な動きは上部肋骨とほぼ変わらないのですが
中部肋骨は鳩尾を起点に動かしていきます。
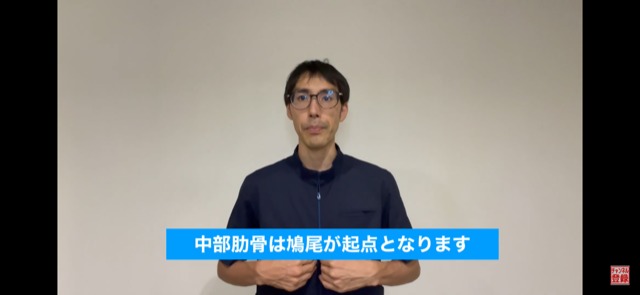
①中部肋骨は前後に回すことはできないので
前後と上下がメインとなります。まずは前後運動です。

②続いて鳩尾を起点に上下に動かします。
動きは鳩尾を起点にして動かすだけで
上部肋骨とやり方は同じになります。
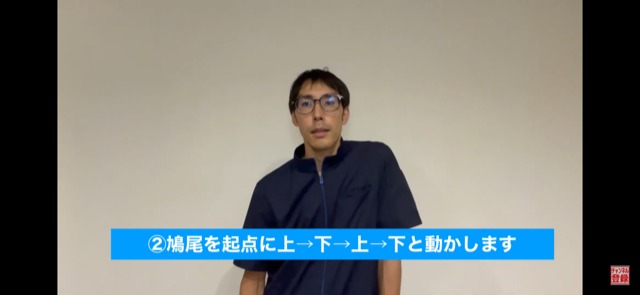
回旋の動きのときが少し複雑で
左と右の肋骨は違う動きになります。
まず回旋を行う前に鳩尾から上と下の2分割にわけます。
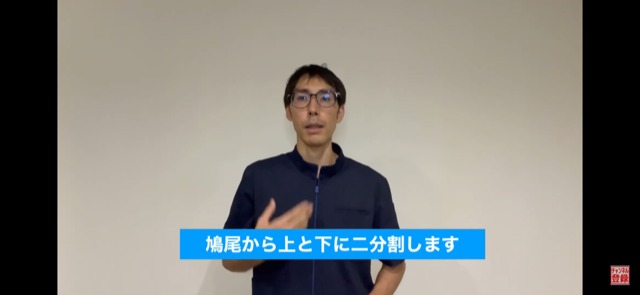
左の上部肋骨が前にいくと
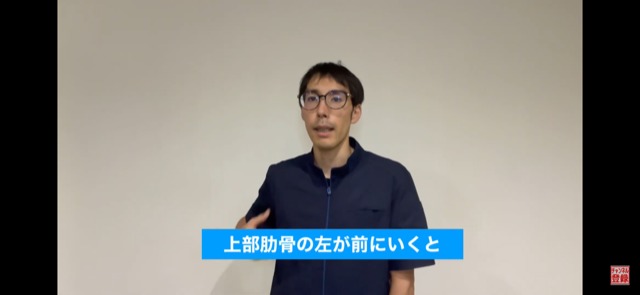
右の下部肋骨は後ろへ回旋します。
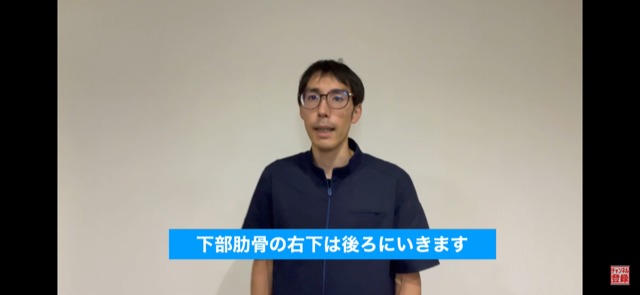
反対に右の上部肋骨を前にすると
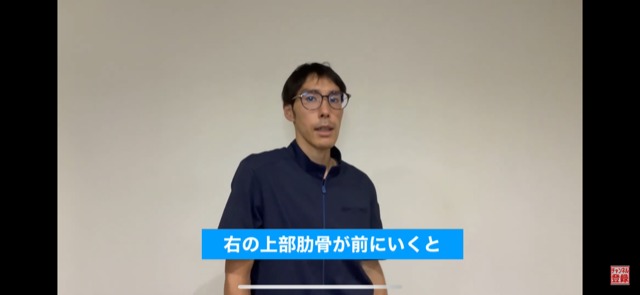
左の下部肋骨は後ろにいくようになります。
この動きを鳩尾を起点にして連動させていきます。
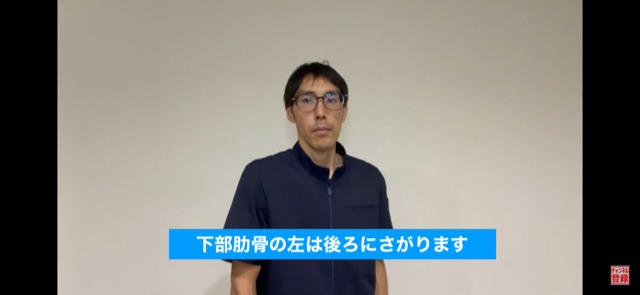
文章だけだとイメージがしにくい
部分もあるかと思います。
動画もありますので動かし方は
そちらをよければご覧ください。
(おまけ)背骨も一緒にイメージするとより動きが良くなる
肋骨の前後の動きは脊椎の
伸展と屈曲の動きに連動します。
お辞儀をする動きは脊椎の屈曲です。
反対に脊椎を反らせる動きは脊椎の伸展です。
これはどこを意識して動かす違いはあるものの
肋骨を前後に動かす動きと同じです。
余裕のある方は肋骨だけでなくこの脊椎も
一緒に動いているイメージをしていくと
背骨も一緒に動いて脊柱の筋肉の
伸縮もしやすくなります。


